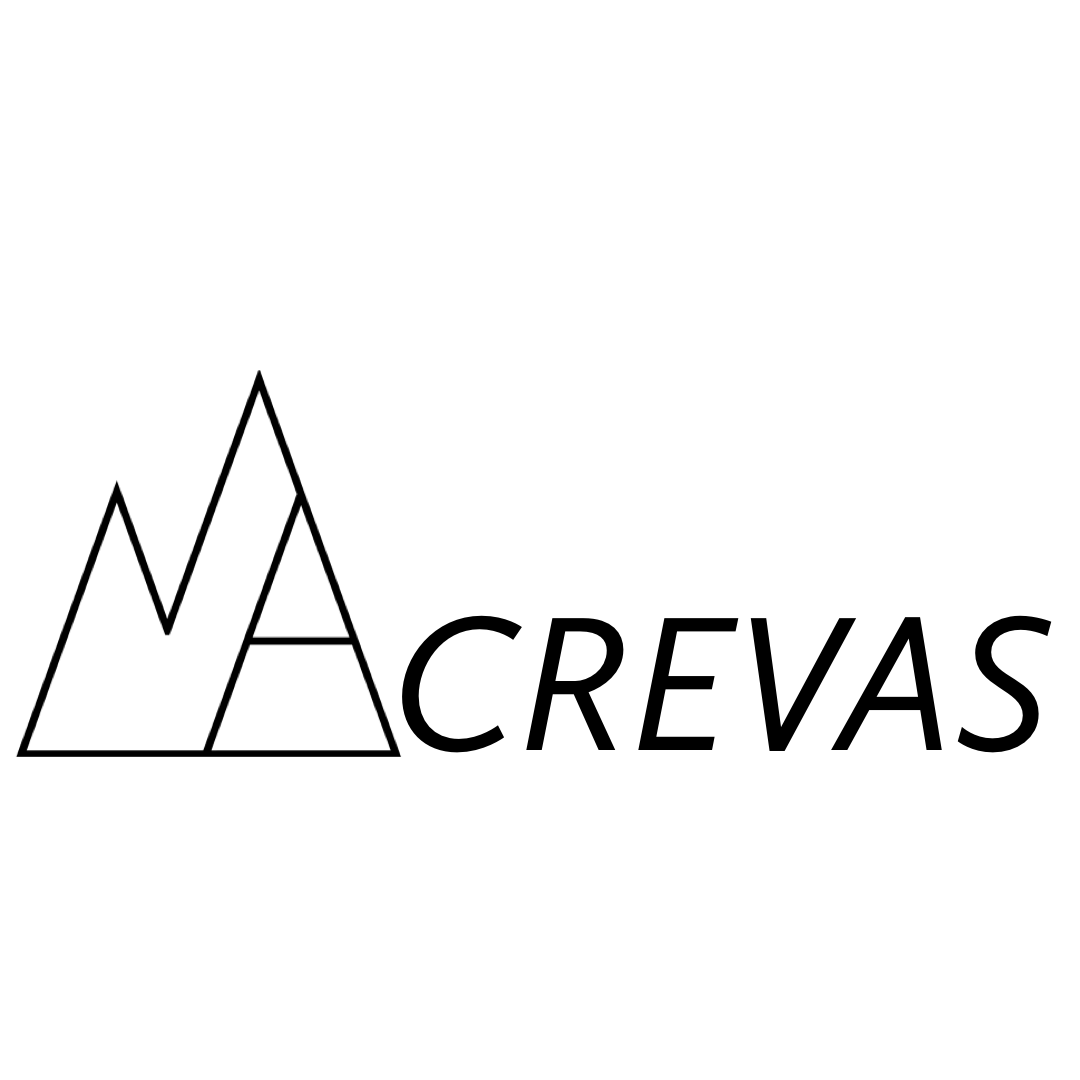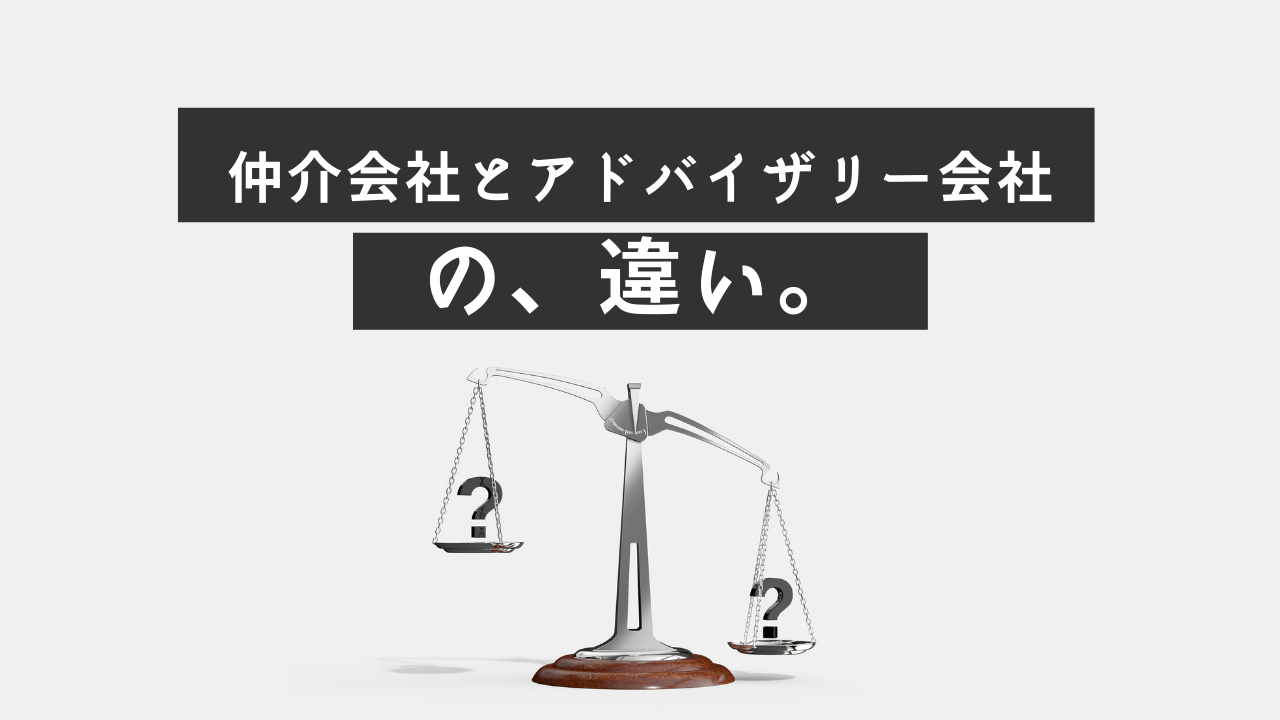
仲介会社とアドバイザリー会社の違い
-2021年01月02日-
M&A会社の種類は大きく分けて
『仲介会社』と『アドバイザリー会社』の2つに分かれます。
仲介会社は、売却側(セルサイド)と買収側(バイサイド)の”両方”、
アドバイザリー会社は、セルサイドであればセルサイドのみの”どちらか一方のみ”とM&Aに係る契約(もしくは情報提供料等の名目)を結んで役務を行います。
簡単に言えば仲介会社は、1件の案件でセルサイドとバイサイドの双方から報酬をもらうため、アドバイザリー会社の「倍」の手数料を得る事になります。
仲介会社が倍の手数料を取るといっても、セルサイドとバイサイドの企業側が
支払う金額の総額は同じなので、仲介会社に頼んでもアドバイザリー会社に頼んでも企業側にとって「お金」の面の有利不利はありません。
では、仲介会社のように「同じM&A会社の人が”両側”に付く」という点で、セルサイド・バイサイドの有利不利について、どんなメリット・デメリットがあるのか?について解説していきます。
同じM&A会社の人が
両側に付くメリット・デメリット
| 表1) | 最低条件 | 基準条件 | 最大値 |
|---|---|---|---|
| セルサイドの希望(売側) | 10億円 | 15億円 | 20億円 |
| バイサイドの希望(買側) | 15億円 | 20億円 | 25億円 |
表1の例で「会社の利益」を考えてみましょう。
この場合、経済合理性だけで言えば
セルサイドはなるべく高く売りたいため
「できるだけ20億円で交渉してくれ」とM&A会社に言い
バイサイドはなるべく安く買いたいため
「15億円で交渉してくれ」とM&A会社に言いますよね。
それに対し、仲介会社やアドバイザリー会社は各々どのように対応していくのでしょうか?
アドバイザリー会社が両側についた場合
セルサイド・バイサイドにそれぞれ別の会社が付くため、各々のアドバイザーが自社のクライアントのために最大限交渉し、金額を折れる代わりに諸条件で飲んでもらう、等の交渉を行った結果、15億円~20億円の間で決着が付くことが想定されます。
デメリットとしては、これは仲介会社にも言えることですが、アドバイザー個人の力量によって有利な条件でまとめられるかどうかが決まるため、誰に頼むかが非常に重要になってきます。
仲介会社の場合
メリットとして、当然セルサイド・バイサイド両方の情報を知っているため、内容がまとまるまでのスピード感は早いです。
デメリットとしては、忖度が行われる可能性があることです。
契約条件に関して、まったく公平に対応する事も可能かもしれませんが、斜に構えて考えると、
例えば、
どちらか一方のクライアントから
・追加で手数料を払うので何とかしてくれ
・譲渡後も顧問として費用を払うのでこちらに有利にしてくれ
などと言われた場合に、そちらに有利な様にしないと言い切れるでしょうか?
例えばバイサイドに対して
「15億円でまとめてくれたら譲渡後も顧問として費用払うよ!」と言われたら、断るでしょうか?
極端な話、「10億円でまとめてくれたから1億円追加でアドバイザー報酬払うよ!」と言われたらどうでしょうか?
その忖度をM&A会社が飲んだ場合、損するのはセルサイドの会社です。
ちなみに欧米では
『仲介』という概念は利益相反のため存在しません。
日本は法規制がないため
法律違反ではありませんので、ダメではないのです。
ちなみに、CREVASのM&A専門家は今まで20件以上FAとして成約していますが「仲介」は1件もありません。仲介をしない理由は『利益相反だから』という綺麗な理由ではなく、CREVASは再生案件(私的整理や法的整理)が多いため、「仲介=債権者への弁済最大化を損なう行為」として認識しているからです。
民事再生手続下においてのFA業務は、FA契約締結においても裁判所が選任した監督委員(弁護士)の同意が必要となり、監督委員は債権者への弁済極大化のために動くため、それを損なう可能性が高い仲介契約の締結を認めない可能性が高いです。(普通に考えれば当たり前の行為であり、仲介契約で同意申請をしたことがないので、許可が出ない事は確認できていませんが。)
仲介会社は、悪?
仲介が「悪」だと言うつもりはまったくありません。
セルサイド側について、その相手であるバイサイドを見つけてこられる情報網はやはり費用を払うに値する「無形の価値」があるものだと思いますし、会社の業務負荷の観点からもセルサイドが調べたものを、またバイサイドが調べるより負荷は少ないですからね。
ただし、上記のような『忖度』が行われる可能性があるという事は認識しておき、そのうえでメリットと天秤にかけて依頼する会社を決めていただければ、と考えています。
終