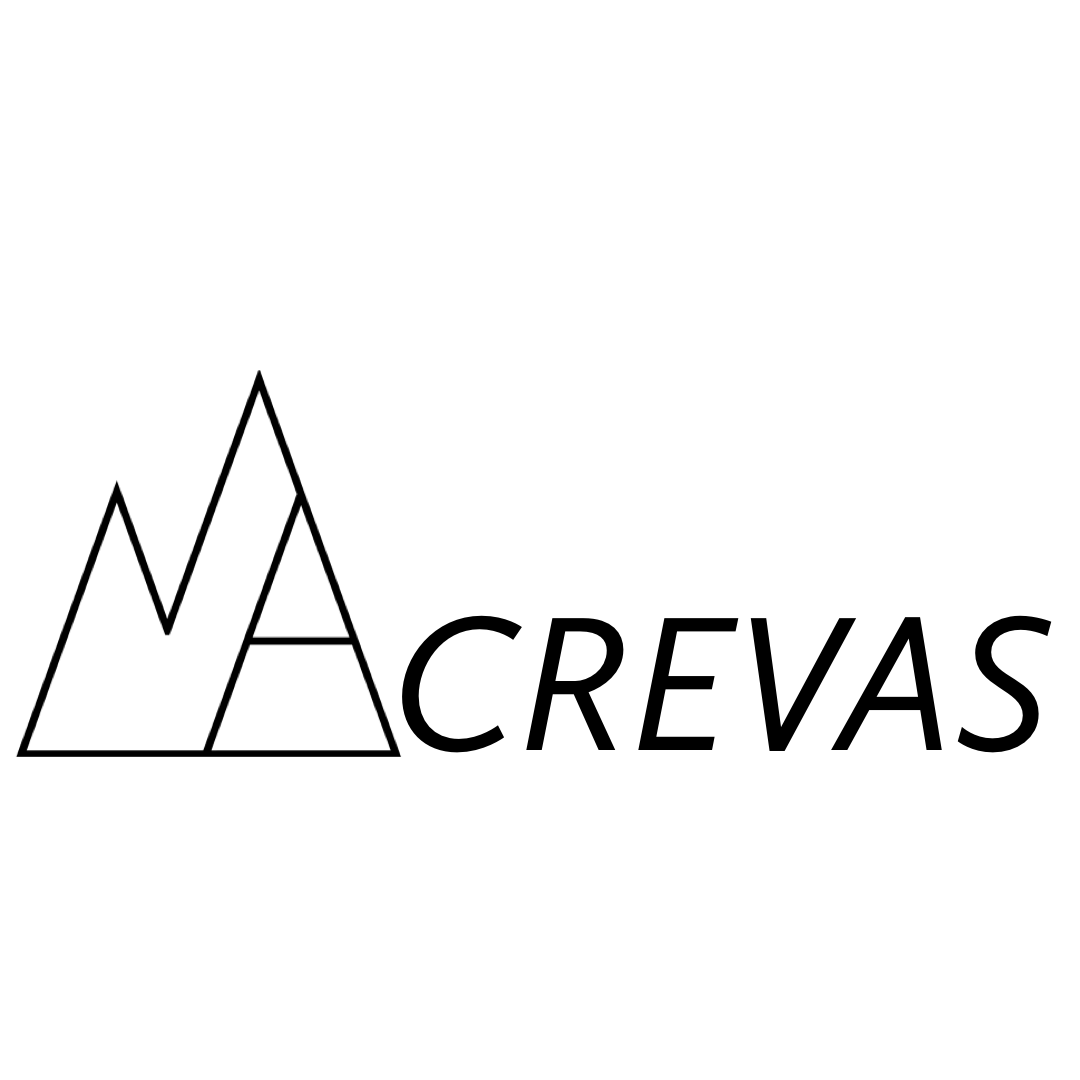M&Aにかかる費用と相場観
-2021年01月02日-
M&Aのフィナンシャル・アドバイザリー業務(FA)に係る費用体系は大きく分けて『月次報酬』と『成功報酬』の2つに分かれます。
月次報酬は、着手金、初期調査費用やリテーナーという名目だったりする事はありますが、M&Aの成否にかかわらず必要な費用で、原則返還されない費用となります。
当然ながら、資料を作成したり等で大きなコストがかかるため、少しの費用(月額~20万円程度)がかかるのは必要であると考えています。
それが仮にゼロだと、企業側が簡単に進めて簡単に辞めてしまう場合も多く、検討してくれた会社に迷惑がかかるため、極端な話1円でも払う事がM&Aに対して真剣になる動機付けになるという理由です。
月額報酬が“異常”に高い
M&A会社には注意
月次報酬をあまりに高い金額で話をしてくるM&A会社については、結果M&Aが成約しなくてもM&A会社にとって損がなく『なんとか決めないと』という本気度が低くなりやすいため、月次報酬額については注意が必要です。
CREVASでは、「月次報酬=役務を行う上での必要経費」であって、結果的にM&Aを成約できれば成功報酬をいただけるため、弊社側でも多少の持ち出しはしょうがないというスタンスで「最低限」の費用負担をお願いしています。
成功報酬は
アドバイザーによって計算式が異なる
成功報酬は
M&Aが成約した場合にかかる費用ですが
その計算方法は、アドバイザーによって異なります。
一般的に下記表の「レーマン方式」によって算出される金額が成功報酬となっていますが、注意すべき点は、あなたが依頼するアドバイザーが「何を報酬基準額としているか?」です。それにより、あなたが支払う成功報酬額は大きく変動する可能性があります。
| 報酬基準額 | 料率 |
|---|---|
| ~5億円 | 5% |
| 5億円超~10億円 | 4% |
| 10憶円超~30億円 | 3% |
| 30億円超~50億円 | 2% |
| 50億円超~ | 1% |
レーマン方式は、
報酬基準額×料率=成功報酬額となり、
計算方法は下記の通りです。
例)報酬基準額が6億円だった場合成功報酬
✖間違った計算方法
6億円×4.0%=2,400万円
〇正しい計算方法
(5億円×5.0%)+(1億円×4.0%)=2,900万円
報酬基準額は複数ありますが、今回はよく用いられる3つをご紹介します。
1.株式価値基準(売却価格)
2.企業価値基準(売却価格+有利子負債)
3.移動総資産基準(売却価格+全ての負債の合計)
・有利子負債=役員借入金や銀行借入金等
・全ての負債の合計=有利子負債+買掛金等の企業負債)
1<3の順に、成功報酬額が高額になりやすいです。
1.株式価値基準
報酬基準額を株式価値基準にしているアドバイザーであれば、「売却価格」にそのままレーマン方式の利率を掛けた金額が成功報酬額になります。
M&A直後に役員退職金を支給する場合は、その金額も報酬基準額に加算されます。
2.企業価値基準
報酬基準額を企業価値基準にしているアドバイザーの場合、「売却価格+有利子負債の合計」にレーマン方式の利率を掛けた金額が成功報酬額になります。
そのため、銀行からの資金調達に大きく頼っている中小企業等は、成功報酬額が高くなってしまいますので、株式価値基準を採用しているアドバイザーに依頼した方が成功報酬額を安く抑えることができます。
3.移動総資産基準
報酬基準額を、移動総資産基準にしているアドバイザーであれば、「売却価格+全ての負債の合計」にレーマン方式の利率を掛けた金額が成功報酬額になります。
そのため、有利子負債(借入金)や企業負債(買掛金等)を多く抱えている企業ほど、成功報酬額が高くなってしまいますので、企業価値基準か株式価値基準を採用しているアドバイザーに依頼した方が成功報酬額を安く抑えることができます。
報酬基準額は事前に確認してから
アドバイザーと契約しよう。
成功報酬においては「何を報酬基準額としているか?」が最も大事であり、ここを事前に確認していなかったために想定以上の成功報酬を請求されたという事例も多くあります。
なので、契約前に「うちだったら成功報酬はいくらなのか?」をしっかり聞くようにしましょう。
金額をうやむやにする先は怪しいですし、ちゃんとしたアドバイザーであれば丁寧に説明してくれるはずですよ。
成功報酬額の相場
中小企業における成功報酬の金額の多寡は
・企業規模
・有利子負債額
・事業部の多さ(煩雑さ)
・難易度
等によって変わってくるため、一概に基準はないですがおおよそ500万円~2,000万円くらいのスポットが多いものと思われます。
CREVASは、事前に自社の売却価格を知った上でM&Aを進めるかご検討いただけます。まずは自社の売却価格を簡易算定してみませんか?
終